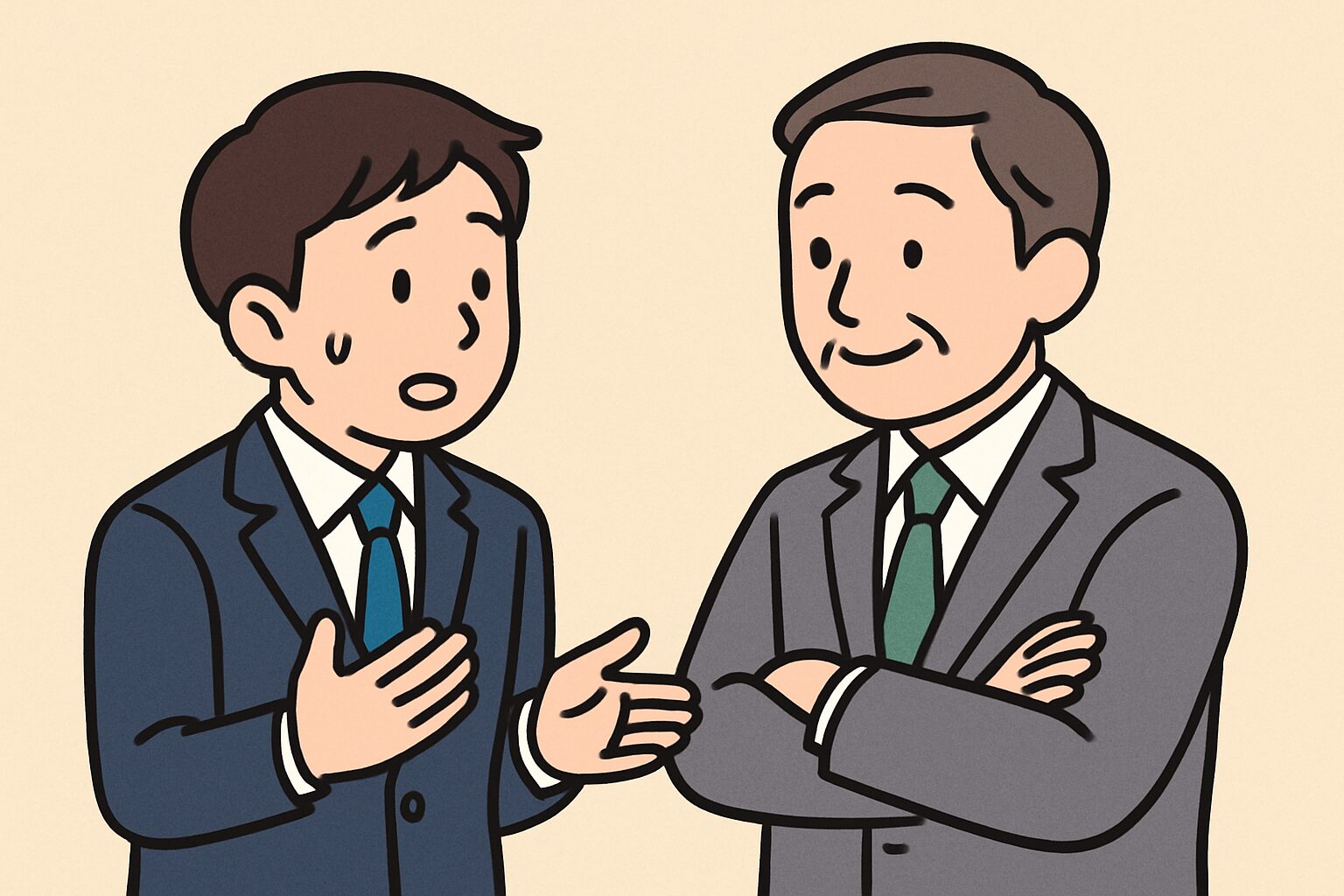職場の飲み会に参加しない後輩たち|断られても気にしない考え方

飲み会に断られて、モヤモヤしているあなたへ
職場の飲み会で、気軽に後輩を誘ったつもりが「すみません、予定があって…」とやんわり断られる──。
頭では「最近の若い世代は飲み会が苦手」と理解しているつもりでも、どこか寂しさや戸惑いが残る。
- 「自分が嫌われてるのかも?」
- 「先輩として頼りにされてないのかも?」
そんな気持ちにモヤモヤする経験、ありませんか?
この記事では、時代とともに変化してきた飲み会文化と、後輩を自然に誘うための考え方を紹介します。
職場の飲み会文化は、こうして変わってきた
昭和:飲み会は「仕事の一部」
上司の誘いは絶対。酒を酌み交わして本音を語るのが、信頼関係を築く手段とされていました。
平成:交流の場へと変化
強制感はやや薄れ、飲み会は仕事仲間とのリフレッシュの場に。ただし「誘われたら断りづらい」空気は残っていました。
令和:個人の自由が優先される時代へ
- プライベートを大事にする価値観
- お酒を飲まないライフスタイル
- 上下関係よりもフラットな関係
「行きたい人だけ行けばいい」というスタンスが当たり前になっています。
コロナ禍が拍車をかけた
2020年以降、外食や会食の自粛ムードにより、飲み会は”なくても困らない文化”として定着。オンライン飲み会など新しいスタイルも生まれ、価値観の変化がさらに進みました。
お酒が苦手な若手が増えている理由
- アルコール体質が合わない
- 健康志向・ライフスタイルの多様化
- “飲まなきゃダメ”という同調圧力がストレスに
「飲まない=付き合いが悪い」という考え方は、今の若い世代には通用しません。
後輩が飲み会を断る心理とは?
- 先輩を嫌っているわけではない
- 仕事外の時間を自分のペースで過ごしたい
- 飲み会に気を遣いすぎて疲れる
「断る=拒絶」ではなく、「選択肢のひとつ」として受け取ることが大切です。
後輩を自然に誘うためのコツ
1. 「無理しなくて大丈夫」と一言添える
- 「来れたらで全然OKだよ」
- 「少しだけ顔出すだけでも大歓迎」
相手にプレッシャーを与えない言い方がポイントです。
2. 飲み会以外の選択肢を用意する
- 昼休みにランチ
- ノンアルで軽くカフェトーク
「飲み会=夜の酒席」だけにこだわらないことで、交流のハードルが下がります。
3. 断られても気にしない
後輩は「飲み会を断った」だけ。 あなたを否定しているわけではありません。
必要以上に気に病まないことが、心をラクに保つコツです。
まとめ|無理に誘わず、自然体でいこう
飲み会文化は、時代とともに変化してきました。
- 昭和:強制参加
- 平成:断りにくい空気
- 令和:自由なスタイル
そしてコロナ禍がその変化を加速させました。
今の若手が飲み会を断るのは、ごく自然な流れです。
無理に誘わず、自然体で接すること。
その中で、心から信頼できる関係が少しずつ築かれていきます。
焦らず、押しつけず、あなた自身も気持ちよく働ける関係を大切にしていきましょう。
関連記事
・先輩が後輩とどう向き合うべきか?
→ “後輩との距離の取り方”についても参考になります。
・後輩が辞めそうなときに先輩ができること
→ 辞めたいと感じている側の気持ちを知るためのヒントになります。